「うちの子、ちょっと発達が遅いかも…?」そんなふうに不安を抱えるママ・パパは少なくありません。他の子と比べて「言葉が出ない」「歩き始めが遅いかも」と感じ、焦ってしまうこともあるでしょう。
でも、実は発達のスピードには大きな個人差があり、日々の関わりを少し工夫することで、安心できる変化が見えてくることもあります。
本記事では、現役保育士の私が「年齢別の発育目安」を分かりやすく整理し、家庭で今すぐできる“安心して見守るための関わり方”をお伝えします。「早くできなきゃ」と慌てず、お子さんが“今”どのように頑張っているかを一緒に見つめ直していきましょう。。
「発達が遅いかも?」と感じるのはどんなとき?

言葉の発達で気になること
- 1歳を過ぎてもあまり喃語が出ない
- 2歳になっても単語が少ない
- 呼びかけに反応が薄い
身体の発達で気になること
- 歩き始めが遅い
- 転びやすい・不安定
- 手先の動きがぎこちない
年齢ごとの発達の目安を知っておこう
個人差はありますが、おおよその発達の目安を知っておくと安心です。焦る必要はありませんが、参考にしてみてください。
1歳前後の発達の目安
- つかまり立ち〜ひとり歩き
- 「まんま」「ブーブー」など意味のある言葉が少し出る
- 名前を呼ばれると反応する
2歳前後の発達の目安
- 2語文が出始める(「ママ きた」など)
- 走る・段差をのぼる
- 簡単なお手伝いができる
3歳前後の発達の目安
- 3語文が出て会話が楽しめる
- 片足立ち・ジャンプができる
- 友だちと一緒に遊ぶ姿が見られる
発達をサポートする家庭での関わり方

発達をうながすには、特別なことよりも日常の中での関わりが大切です。
言葉の発達を育む関わり
- 子どもの言葉をくり返して共感する(「ワンワン!」→「ほんとだね、ワンワンいたね」)
- 絵本の読み聞かせを毎日少しずつ
- 指差しやジェスチャーも「伝えようとする気持ち」として受け止める
身体の発達を支える関わり
- 外で体を動かす遊びを取り入れる
- 手遊びや積み木など指先を使う遊びを楽しむ
これは、遊びだけでなく、顔を洗う・ボタンを自分ではめるなどの動作からも習得できます - 「できた!」を一緒に喜び、自信を育てる
【重要】全般的な関りの意識として
- 環境を整え、自律性を最大限にサポートする
大人がまず行わなければならないのは、子どもが活動しやすいように環境を整えることです。
① 子どもが使いやすいものを揃える: 子どもが使用しやすいさいずの机や椅子、つかみやすいハサミやノリなど、子どもが必要なものを揃えてあげましょう。
②「見守る」姿勢を徹底する: 子どもが何かに集中して取り組んでいる場合は、口を出さずにただ見守るだけにします。大人から見て「失敗」しそうな場合でも、先回りして失敗を回避させるようなことはしてはいけません。また、集中しているときには「すごいね」「上手ね」などの声掛けも、親の自己満足なだけです。控えめにしましょう。 - 失敗から自分で訂正する力を養う
生き方の基礎となる体験を提供する上で大切なのは、子どもが失敗に気づき、それを自分自身で訂正させる力をつけさせることです。
何かお手伝いをしてもらう時(料理や洗濯物たたみなど)も、最初は失敗だらけになるかもしれませんが、余計な口を挟むとやる気がなくなり、次から手伝ってもらえなくなる可能性があります。多少の失敗には目をつぶり、子どもが主体となって取り組む姿勢を尊重しましょう。 - 成長の時期に基づいた関わりをする
子どもには、ある特定の事柄に対して強く反応し、吸収する大切な時期があると言われています。
例えば、3歳から6歳頃までは、視覚や聴覚などの五感に関する成長が著しい時期にあたります。
6歳頃までは言語の成長の著しい時期にあたります。
この簡単に吸収できる大切な時期に合わせた関わり方をすることが、大切とされています。
その時期にあった玩具や絵本、遊びを工夫してみましょう。 - 自律的な行動を促すための家庭での工夫
子どもが自分自身で物事を進められるよう、家庭で工夫を行うことも、自律性を育てる上で効果的です。
①物の置き場所を決める: おもちゃや絵本などは、常に同じ場所にあるように決まった場所を作りましょう。いつも同じ場所にあれば、子どもが自分で取り出せます。
② ルーティーンを活用する: 2~3歳頃は、同じ手順で同じ行動を繰り返すのが大好きな時期です。保育園に行く前の準備のように、ルーティーンを自分で出来るよう、決めましょう。
③褒めるより共感する: 子どもが何かできた時に大げさに褒める(例:あまり頑張っていないのに「すごい!」といったり)と、むしろ逆効果になることがあります。子どもがたくさん喜んでいる時は、同じ程度にたくさん喜んで共感するほうがとても重要です。
④ 親が手本を示す: お手伝いをしてもらう際など、何かを教えるときには、親がゆっくりやってみせることが大切です。やってみせている間は、あまり喋らないようにしましょう。
★発達の遅れを感じた際には、まず子どもの「したい」という気持ちを尊重し、指先を使う活動や、失敗を恐れず自分で試行錯誤できるような環境を整えることが、子どもの潜在的な能力を引き出すサポートにつながると考えられます。
それでも気になるときは悩みすぎずに相談を

成長には個人差がありますが、心配が続くときは専門機関に相談してみましょう。子どもに合ったサポートが受けられることもあります。
相談できる場所の例
- 市区町村の保健センター(発達相談)
- かかりつけ小児科
- 発達支援センターや療育機関
- 保育園・こども園の担任保育士
まとめ|「ゆっくり」でも大丈夫。見守る力が成長を支える

子どもはそれぞれのペースで成長します。
他のお子さんと比較して焦ってしまうママからよく相談されますがほとんど数か月で追いつき、逆に追い越してしまうこともあり、悩む必要はなかったということがほとんどです。
環境を整えたり、声がけを変えただけでもぐんと成長することもあります。子どものせいではなく大人が原因ではないかも考えましょう。
また、焦る気持ちは自然ですが、「できない」より「できるようになる途中」を見つめていきましょう。毎日の関わりが、確実に子どもの力になっています。
焦る、心配する気持ちからイライラして子どもへの態度にあらわれる事こそ、子どもの成長を妨げます。子どもは想像以上にママの表情に敏感です。
健やかに育って欲しい思いがあるなら、おおらかな子育てを心がけましょう。
あわせて読みたい関連記事
発達を支えるおすすめアイテム
遊びながら「ことば」や「体」の発達を促すおもちゃもおすすめです。保育士としても実際に使って良かったものをご紹介します。
1歳〜2歳におすすめ:音や手触りを楽しむおもちゃ
▶︎ 森の音楽会(エド・インター)
木の温かみがあり、たたいたり転がしたりしながら音の変化を楽しめます。指先を使う練習にもぴったり。
2歳〜3歳におすすめ:ごっこ遊びや言葉を広げるおもちゃ
▶︎ アンパンマンおしゃべりいっぱい!ことばずかん
タッチペンで遊びながら言葉が増える人気の知育玩具。発語を促すきっかけづくりにも役立ちます。
おうち遊びにおすすめ:体を使って発達をサポート
▶︎ 室内ジャングルジム(折りたたみタイプ)
雨の日でも体を動かせる!バランス感覚や筋力アップにも◎
さいごに
親は環境を整えて愛情を注ぐことが役割。そこが出来ていれば「うちの子、ゆっくりだけど確実に成長してる」と思えるように、焦らず関わっていくだけ。 子どもは想像以上にママの表情に敏感です。 健やかに育って欲しい思いがあるなら、おおらかな子育てを心がけましょう。 日々の小さな積み重ねが、子どもの未来の力につながります。

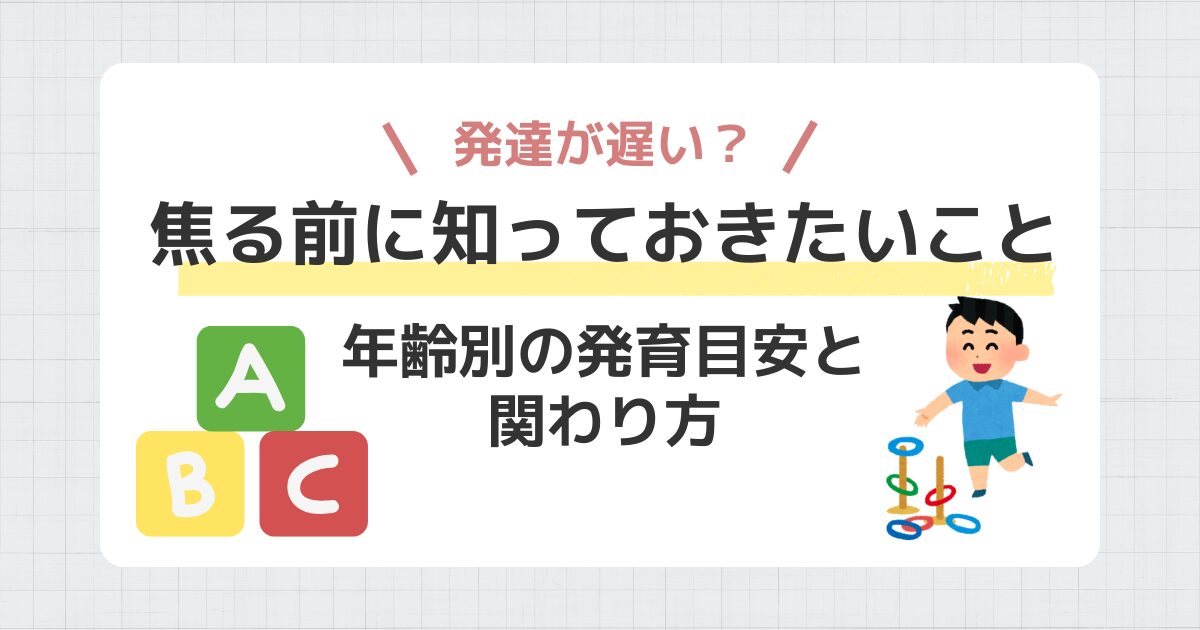
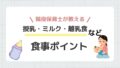
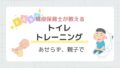
コメント