「寝かしつけが大変…」「昼寝をしてくれない」そんな悩みはどこのご家庭にもあると思います。
私も自分の子育ての時はとても大変で、いらいらの負のスパイラルが子どもに悪影響を与えることを心配する日々でした。
その後の人生の保育士経験の中で、冷静にいろんなお子さんのお昼寝をみるにつけ感じた寝かしつけのポイント、その中から「家庭でも試しやすい寝かしつけルーティン」を5つご紹介します。

環境を整える:明るさ・音・温度を一定に
寝る前の環境が整っていると、子どもは「もうねんねの時間なんだ」と感じやすくなります。
・部屋を少し暗くする(豆電球1つ程度)
・静かな環境にする(テレビや話し声をオフ)
・温度は20〜22℃前後、湿度は50〜60%が目安
保育園でも毎日同じ環境をつくることで、自然と眠くなるリズムを身につけるようにしています。
眠る前の「いつもの合図」(ルーティン)を決める
たとえば「絵本を読む」「子守唄を歌う」「トントンする」など、
毎回同じ“寝る前の合図”を作ることで、安心感が生まれます。
絵本はベッドルームにも数冊用意しておきましょう。私のシッター先のおこさんは寝る前の『よるくま』(偕成社)の読み聞かせが大好きです。かわいいくまと優しいママのお話で、安心と優しい気分で眠りにつきます。

また、子供の胸を優しくとんとんしながら子守唄を歌うのも有効です。低めのやさしい声がいいですね。保育園の子どもは、眠くなると横になり、自分で胸をとんとんしながら寝て行くお子さんもいてかわいらしいです。それほど安心のルーティンなんでしょうね。
寝かしつけグッズとしておすすめなのは、ぬいぐるみ付きガーゼなど。肌ざわりがよく安心材料になります。お気に入りのねんねグッズがあるとそれを触っているだけで眠れるので、ひとつそれがあるととても便利です。旅行や帰省の時も持ち出せるものがいいですね。
ママの耳たぶやママの二の腕が安心材料という子どももいますが、常にママが横にいるとは限りません。ママが忙しい時のために、グッズを探しましょう。
寝る時間をできるだけ固定する
たとえば1歳前後は、体内時計が少しずつ整う時期。
昼寝・夜寝の時間を毎日同じくらいにすると、眠りが深くなります。
保育園では「12:30〜15:00」など一定時間を徹底しています。家庭でも「お昼ごはんのあとに寝る」など、流れを決めましょう。
ご参考までに年齢別の睡眠時間の目安です。
| 年齢/月齢 | 1日の睡眠時間の目安 | 補足・昼寝など(目安) |
|---|---|---|
| 新生児〜3か月 | 14〜17時間 | 昼夜を問わず断片的な睡眠が多い時期です |
| 4か月~11か月 | 12~15時間 | 午前・午後・夕方にお昼寝をすることも多いです |
| 1歳~2歳 | 11~14時間 | 昼寝は1回が一般的、2回取る子もいます |
| 3歳~5歳 | 10~13時間 | 昼寝をしない子も出てきます。昼寝は30分~2時間程度まで |
| 6歳以上 | 9~12時間 | 昼寝はほとんど不要。夜の睡眠を重視です |
この表は「だいたいこんなふうに成長するよ」との見通しをもって安心してもらうためにつくりましたが、全くこのような経緯をたどるとは限りません。
うちの子は違う。。。といって焦ることは禁物です。
「眠れない日」も焦らない
どうしても眠らない日もあります。そんな時は、無理に寝かせようとせず「横になって静かに過ごす」だけでもOK。横になるだけでも身体がやすまるので。
焦る気持ちは子どもに伝わってしまいます。眠らないことの成長への影響よりも、ママのイライラの影響のほうが絶対NGです。
保育士も「今日は眠くない日なんだ」と受け止め、リズムを崩さないことを大切にしています。
3日も4日も眠らない子どもはいませんから。
親の声かけが“安心スイッチ”に
眠れないとき、子どもが一番求めているのは“安心”。
「大丈夫」「ママ(パパ)ここにいるよ」と短く優しく声をかけてあげてください。
声のトーンを少し低めにすると、安心感が伝わりやすいですよ。
声のトーンとスピード
優しい低めの声で、ゆっくり話すことが大切です。「おやすみの時間だよ」「今日はいっぱい遊んだね」など、短く落ち着いた言葉でOK。
肯定・共感の言葉を使う
「大丈夫だよ」「そばにいるよ」と、子どもの気持ちを受け止める言葉をかけることで安心感を高めます。「ねんねしなさい」ではなく、共感型の声かけがおすすめです。
触覚と組み合わせる
背中や胸を軽くトントンしながら声をかけると、安心感が増します。手を握ったり肩に軽く触れるだけでも効果があります。
ルーティン化する
毎日同じ言葉やメロディで声かけすると、“ねんねの合図”として子どもが認識します。習慣化することで寝かしつけがスムーズになります。
寝る前の「褒めポイント」を入れる
「今日はたくさん遊んだね」「絵本最後まで読めたね」など、達成感や安心感を声で伝えると子どもは落ち着きやすくなります。
心理的安心感を意識
保護者自身がリラックスしていると、子どもも安心します。表情や呼吸も穏やかにして声かけすると効果的です。
まとめ|寝かしつけは「がんばる」より「整える」
寝かしつけは、努力よりも“リズムと安心感”がカギ。
環境を整える、安心グッズを整える、時間を整える、そしてママの気持ちも整える…。
保育士の現場でも「眠ること=育ちの一部」として大切にしています。
寝ないからといって焦ったりイライラするのは禁物。決まった時間に寝かしつけるのを意識しても無理な時は「ま、いいか」と。
限られた子育ての時間のなかの一部として、お子さんと一緒に、ゆったりした寝る時間を楽しんでください。





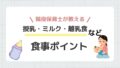
コメント